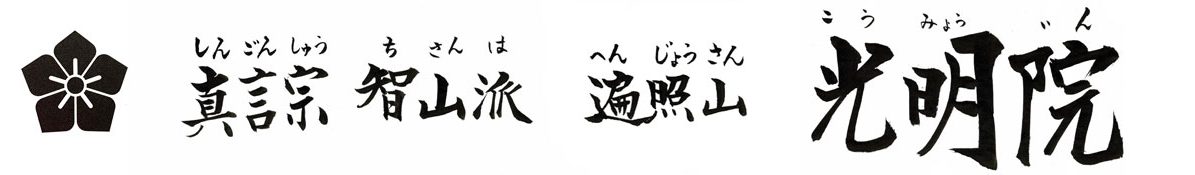光明院は真言宗智山派に属し、本尊は不動明王を祀る360年以上の時を刻む寺院である。光明院墓所内にある最古の墓は正保3年(1646年)と刻まれている墓地である。
山門入り左手にある、弘法大師千五十回忌御遠忌の記念碑を見ると、明治15年12月に光明院住職 石井祐道師・本寺龍泉寺住職 森田竜海師・前住職 川口町東明院住職 田口真融師 さらには当家19代として海老原茂左衛門と刻まれて、寺同士のつながりの深さや檀信徒の心の寄りどころとされていたのがわかる。
檀徒の心のより所として葬儀、法事、祈願を行い、更には誰でも参加が出来る、ご詠歌、写経、書道教室を行い地域に開かれた寺となっている。

当山は360年以上前に創建されたとされる真言密教のお寺です。平成16年6月28日今の住職(荒井正道)が住職となり再興、現存する本堂は平成6年11月に建設された建物です。真言宗智山派に正式に登録され一寺院としての承認を賜ったのち、宗教法人格取得が困難といわれている世の中において、平成21年5月7日埼玉県知事・上田清司氏より宗教法人の許認可を受けました。

平成22年3月1日本堂内に預骨施設 「安穏の間」を設置。 平成25年2月28日には永代供養墓「感謝の塔」を建立。さらに境内を全面バリアフリーして、車椅子の方でも安心してご参拝頂けるように環境を整備して今に至ります。

本堂・庫裡落慶に伴い、本堂内や両祖大師 【弘法大師・興教大師】(元禄15年12月14日作 《赤穂浪士討ち入りの年》)の修復が行われた際、剥げ落ちた色を塗りなおしたが、興教大師の塗りだけは何度塗っても赤い筋が浮き出てしまいました。ある地元住民の伝承話があります。「明治時代の廃仏毀釈の折、心無い住民が光明院の仏像を壊そうという騒動が起こった際に、御堂を守っていた老婆が身を挺して興教大師像を守った。その老婆は、像を守った時に頭を棒のようなもので殴られて、傷を負ってしまう。心無い住民は、命をなげうってでも仏像を守ろうという老婆の姿に恐れをなして、その場を離れていった。》この話を聞いた当時の住職が懇ろに経をあげて供養して再度塗りなおすと、不思議と頭の赤い線が出ることはなかったといいます。